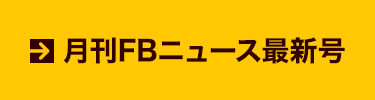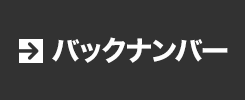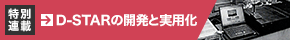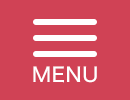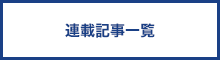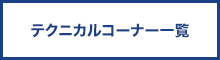アマチュア無線の今と昔
第32回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ
2025年7月1日掲載
連載32回目です。この記事が世に出てからすぐに6m AND DOWNコンテストが開催されます。この記事を読んでくださっている方の中にも、参加される予定の方が大勢いらっしゃると思います。
アイコムからIC-905が発売になってからは、コンテスト(マルチバンドでエントリーしたとき)で勝つためのマストアイテムと言われる程になってきているのではないでしょうか。私も例年のように近所の社団局で参加させてもらう予定です。もしQSOできましたらよろしくお願いしますhi では、今回も進めて参りましょう。

IC-905(アイコム株式会社Webサイトより)
コンテストに参加して思うこと
カムバックしてから、コンテストクラブからお誘いを受け、末席ながら参加させていただいています。昔からコンテストは好きで、いろいろなコンテストに参加して参りました。いろいろといっても主に参加していたのは国内のコンテストです。(海外は呼びに回ってエンティティ稼ぎでしたがhi)
昔と比べて、あきらかに違うと感じる点ですが、50MHzの重要性が下がったこと、それと430MHzのFMの重要性がものすごく高くなったことが上げられます。

アイコム ID-50 ハンディ機1台でもコンテストに参加可能です
特に430MHzはSSBには誰もいなくてもFMにはいる、という現象が起きています。430MHzに限れば、FMとCWだけでいいと思えるほどです。特にCWは、普段はほとんどいない割にコンテストともなるとCWフィルターが必要じゃないかと思えるほど沢山の局が出てきます。これも地域によっては変わってくるかと思います。
CWは1200MHzも430MHzと同じ傾向ですが、関東地方以外は関西エリアであっても閑古鳥が飛んでいるそうです。関東地方、特に東京近郊では、1200MHzのCWでは3時間で100局はいけますが、関西地方の方に話をすると、みんな驚かれます。昔の現状しか知らなかった私は、ホント、浦島太郎状態でした。
コンテストの時にアクティブになるのはいいのですが、普段からもっとオンエアしておかないと、2次業務に格下げされてしまったように、他の業務に持っていかれてしまいます。もしかして、1.8MHzや7MHzのバンド幅が拡がったのもそのせいなのでしょうか? (これはこれでありがたいですが) 先輩達から受け継がれたアマチュアバンド、普段からアクティブにオンエアするようにしたいものです。
落雷について
アマチュア無線家の大敵は、台風の時のような強風と雷ではないかと思います。中にはこれらよりももっと怖い存在(何とは申しませんが・・・)があるようですhi
さて、今回の話題は雷です。雷は、大自然が織りなす最も劇的で美しい現象の一つですが、同時に甚大な被害をもたらす可能性も秘めています。直撃はもちろんのこと、近くに落雷しただけでも無線機などに被害があります。ここでは、雷の発生原因から、いつ、どこで発生しやすいのか、雷の予兆、そして落雷による被害を受けないための具体的な方法について、まとめてみたいと思います。

落雷は写真で見ると美しいんですけどねぇ
1. 雷の発生する原因
雷の発生には、積乱雲(いわゆる雷雲)の内部で起こる電荷の分離が不可欠です。この電荷分離のメカニズムは複雑ですが、主に以下の要素が絡み合って発生すると考えられています。
・積乱雲の形成と発達:
地表が太陽光によって暖められ、暖かい湿った空気が上昇すると、上空で冷やされて水蒸気が凝結し、積乱雲が形成されます。この上昇気流(上昇する空気の流れ)は非常に強く、雲の頂上は対流圏界面に達することもあります。
・氷晶と過冷却水滴の衝突:
積乱雲の内部では、0℃以下でも凍らない過冷却水滴と、すでに凍っている氷晶が共存しています。強い上昇気流と下降気流によって、これらの粒子が激しく衝突し、摩擦を起こします。
・電荷の分離:
衝突の際、比較的重い氷晶はマイナスに帯電し、軽い過冷却水滴や霰(あられ)はプラスに帯電しやすいことが分かっています。重いマイナス電荷を持った粒子は下降気流に乗って雲の下部に集まり、軽いプラス電荷を持った粒子は上昇気流に乗って雲の上部に集まります。結果として、雲の下部はマイナス、上部はプラスに帯電し、地表は誘導されてプラスに帯電します。
・放電(雷):
雲の中や雲と地表の間で電荷の差が限界に達すると、その差を解消するために、目に見える形で電流が流れます。これが「放電」、すなわち雷です。一般的に、雲の下部のマイナス電荷と地表のプラス電荷の間で発生する雷を「落雷(対地放電)」と呼びます。
2. いつ、どの地域で発生しやすいのか
雷は年間を通して発生する可能性がありますが、特定の時期や地域で発生しやすくなる傾向があります。
・時期:
夏: 日本では、夏季に最も雷が多く発生します。これは、太平洋高気圧の縁辺に沿って暖かく湿った空気が流れ込み、地表の加熱によって積乱雲が発達しやすいためです。特に、日本の本州付近では、夕立として局地的な雷雨が多く見られます。
冬(日本海側): 冬の日本海側では、「冬の雷」と呼ばれる特有の雷が発生します。大陸からの冷たい季節風が日本海を渡る際に水蒸気を補給し、不安定な大気状態で積乱雲が発達するために発生します。この雷は、夏の雷に比べて放電規模が大きく、被害をもたらしやすい傾向があります。
・地域:
内陸部: 夏場は、海からの湿った空気が内陸部に入り込み、山岳地帯などで局地的に暖められることで積乱雲が発達しやすくなります。
山間部: 山岳地帯は、地形の影響で上昇気流が発生しやすく、雷雲が発達しやすい傾向にあります。
日本海沿岸(冬季): 上述の通り、冬季は日本海沿岸で雷が多く発生します。
都市部: ヒートアイランド現象により、都市部では周囲よりも気温が高くなりやすく、積乱雲の発達を助長することがあります。
3. 雷の予兆
雷の接近には、いくつかの予兆があります。これらのサインに気づくことで、早期に安全を確保することができます。
・空の変化:
積乱雲の発達: 空に黒く巨大な積乱雲が見え始めたら注意が必要です。雲の頂上がドーム状に盛り上がっていたり、金床のような形(かなとこ雲)をしていたりする場合は、非常に発達した雷雲の証拠です。

積乱雲 入道雲ともいいますネ
暗雲の接近: 急に空が暗くなり、遠くで雷鳴が聞こえ始めたら、雷が接近しているサインです。
・音の変化:
遠雷: ゴロゴロという低い音が遠くから聞こえてきたら、すでに雷は発生しています。光ってから音が聞こえるまでの時間を数えることで、雷までの距離を概算できます(音速は約340m/秒なので、3秒で約1km)。
・空気の変化:
ひんやりとした風: 雷雲の接近に伴い、急にひんやりとした強い風が吹き始めることがあります。これは、雷雲からの冷たい下降気流によるものです。
急な雨や雹(ひょう): 雷雲が接近すると、突然強い雨が降り出したり、雹が降ってきたりすることがあります。
・電磁気的な影響:
髪の毛が逆立つ、肌がピリピリする: 空中の電位差が非常に高くなると、髪の毛が逆立ったり、肌がピリピリしたりすることがあります。これは非常に危険なサインであり、すぐに安全な場所に避難する必要があります。
金属音がする: 周囲の金属物が共鳴して音を発することがあります。
アマチュア無線の今と昔 バックナンバー
- 第39回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ
- 第38回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ
- 第37回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ
- 第36回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ
- 第35回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ
- 第34回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ
- 第33回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ
- 第32回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ
- 第31回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ
- 第30回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ
- 第29回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ
- 第28回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ
- 第27回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ
- 第26回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ
- 第25回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ
- 第24回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ
- 第23回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ
- 第22回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ
- 第21回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ
- 第20回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ
- 第19回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ
- 第18回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ
- 第17回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ
- 第16回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ
- 第15回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ
- 第14回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ
- 第13回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ
- 第12回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ
- 第11回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ
- 第10回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ
- 第9回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ
- 第8回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ
- 第7回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ
- 第6回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ
- 第5回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ
- 第4回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ
- 第3回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ
- 第2回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ
- 第1回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ
外部リンク
アマチュア無線関連機関/団体
各総合通信局/総合通信事務所
アマチュア無線機器メーカー(JAIA会員)