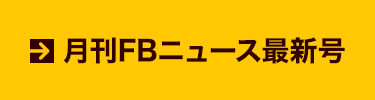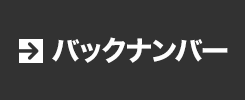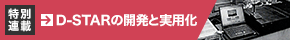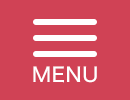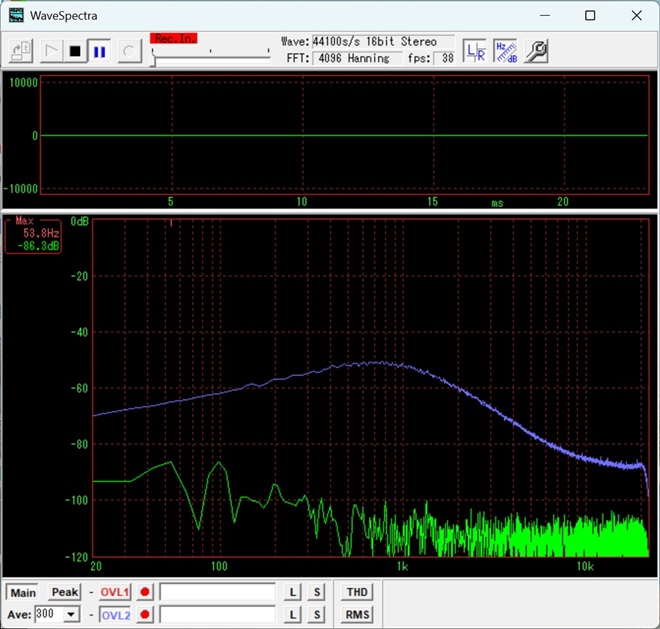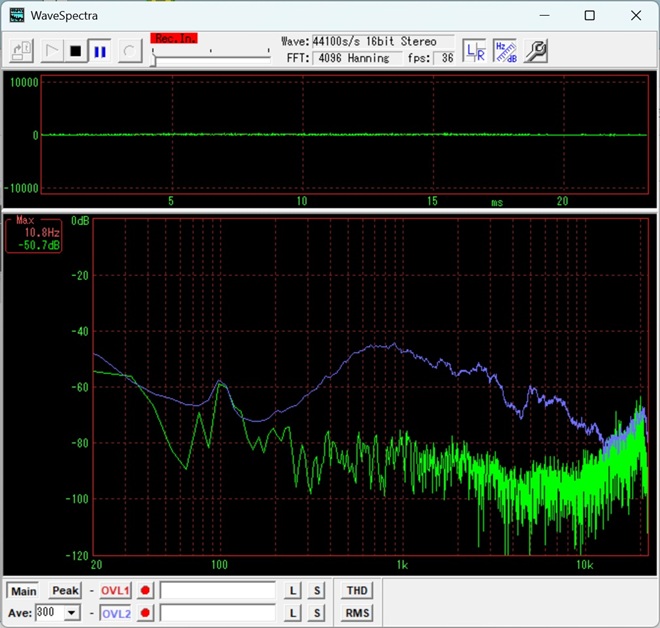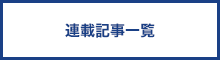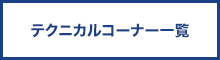新・エレクトロニクス工作室
第41回 疑似音声用アンプ&スピーカ
2025年9月16日掲載
測定
まず、疑似音声をライン入力すると図2のようになりました。これは疑似音声の出力そのものの特性になります。緑のラインは測定終了後に入ったノイズです。これは無視して下さい。青色ラインが測定した結果の平均値です。
作ったアンプとスピーカを通して、パソコンのマイクに入力しました。写真9はその様子です。これをWSでチェックすると、図3のような特性になりました。ヘッドホン用とはいえ、低音のレベル低下は大きいようです。100Hz付近にノイズがあるのは仕方ないのでしょう。高音域はクセだらけで、理想とは思いません。図2との差はスピーカとマイクを通った結果になります。相違はありますが、これでもかなり良い方です。

写真9 疑似音声をスピーカから出している様子
使用感
これでマイクを内蔵したトランシーバの測定も何とかできるようになりました。もちろん理想には程遠いのですが、今後少しずつ進化させたいものです。
このようなスピーカを使った工作をしてみて、今まで全く考えていなかった事もあり勉強になりました。接続すれば音が出るのがスピーカと思っていましたが、ボックスに入れるだけで音域が全く変わります。また、別の事(第21回 KT0936を使ったDSPラジオ)もあって、スピーカのボイスコイルの抵抗はインピーダンスに近い値になるとか、スピーカには最低周波数のf0があるとか、周波数によってインピーダンスの変化があるとか、結構な勉強になりました。実は、ボイスコイルは1kHzとかで8Ωになり、DC的には0Ωかと思っていました。しかし、これでは低音が入った時に大電流が流れてしまいますし、高音が出なくなってしまいます。オーディオが趣味の方には常識なのでしょう。
新・エレクトロニクス工作室 バックナンバー
- 第46回 令和版 熊本シティスタンダードSSBジェネレータ
- 第45回 クリスタルフィルタチェッカ その2
- 第44回 クリスタルフィルタチェッカ その1
- 第43回 基板で作るクリスタルフィルタ
- 第42回 基板で作るアッテネータ その2
- 第41回 疑似音声用アンプ&スピーカ
- 第40回 50MHz用ミニリニア(その1 2SC1970)
- 第39回 基板で作るアッテネータ その1
- 第38回 50MHzマッチングチェッカ
- 第37回 VMP-4を使った50MHzリニアアンプ
- 第36回 GPSDO用出力分配器
- 第35回 4分配器の実験
- 第34回 SG用+28dBmアンプ
- 第33回 DBMチェッカ2
- 第32回 SG用30dBアンプ
- 第31回 50MHz AMトランシーバ2
- 第30回 LA1201テストボード
- 第29回 電源用ダミー
- 第28回 猛暑時のミニ工作 その2
- 第27回 10dBアンプの実験
- 第26回 Si5351A試験ユニット
- 第25回 ACアダプタ風ミニ電源2&専用ダミー
- 第24回 オールバンド・ダミーアンテナ
- 第23回 テレビ用ブースターアンプ
- 第22回 SG用AMアダプタ
- 第21回 KT0936を使ったDSPラジオ
- 第20回 50MHz AMトランシーバ
- 第19回 SG用20dBアンプ
- 第18回 50MHz PSN SSBトランシーバ
- 第17回 GPSモジュール用試験器
- 第16回 猛暑時のミニ製作集
- 第15回 AD9959を使ったSG その2(後編)
- 第14回 AD9959を使ったSG その2(前編)
- 第13回 10MHz GPS発振器2
- 第12回 RF部テストボード
- 第11回 Si5351Aを使ったVFO実験ボード2
- 第10回 IF部テストボード
- 第9回 定電流Ni-MHチャージャー
- 第8回 AF部&電源部テストボード
- 第7回 DBMチェッカ
- 第6回 Si5351Aを使ったVFOの実験ボード
- 第5回 ミニ電源用ダミー
- 第4回 ACアダプタ風 ミニ電源
- 第3回 10.000MHzクリスタルフィルタ
- 第2回 レベル比較器
- 第1回 モールス練習用低周波発振器
外部リンク
アマチュア無線関連機関/団体
各総合通信局/総合通信事務所
アマチュア無線機器メーカー(JAIA会員)