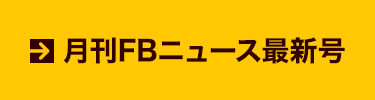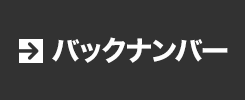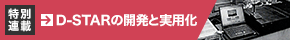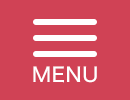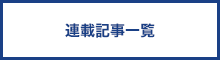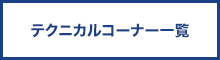アマチュア無線の今と昔
第27回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ
2025年2月3日掲載
連載27回目です。1月も半ばを過ぎてきますと、すっかりお正月気分は抜けてしまいます。今年は例年以上に慌ただしかったですね。仕事あり、インフルエンザありで、お陰で正月休みをゆっくりと過ごせた感じがしませんhi
どんど焼き
さて、毎年感じることなのですが、使い終わったお正月飾りをどう扱えばいいのか? です。実家にいたときは「どんど焼き」というイベントがあり、そこで正月飾りを燃やし、その火でダンゴを焼いて食べていました。このダンゴを食べると病気にならないと言われていた気がします(なにせ50年以上も前の記憶なのでhi)。
というわけで、どんど焼きについて、調べてみました。お正月飾りを集めて燃やすイベントですが、一般的に「どんど焼き」と呼ばれている、日本の伝統的な行事の一つです。
どんど焼きは、小正月(1月15日頃)に行われることが多い火祭りで、お正月飾りや書き初めなどを燃やし、一年の無病息災や五穀豊穣を祈願する行事です。地域によっては、「左義長」「とんど」「焼き初め」など、様々な呼び名で呼ばれています。私の住んでいる地域では、今年は1月10日に行われていました。ずいぶんと早いな~って思っていました。消防車が来ていたのは、イマドキだな~って思ってしまいましたhi
どんど焼きの起源は諸説ありますが、古くは歳神様(としがみさま)を送り出すための「送り火」の意味合いがあったと考えられています。お正月飾りには歳神様が宿るとされ、それらを燃やすことで歳神様を感謝とともに送り出し、新しい年を迎える準備をするという意味が込められています。
どんど焼きでは、集められたお正月飾りや書き初めなどを積み上げ、それに火を付けます。この火に当たることで、一年の無病息災や家内安全が祈願されると言われています。地域によっては、どんど焼きの火で餅を焼いて食べたり、お菓子を配ったりする地域もあります。昔はどこの地域にも畑や田んぼがありましたので、どんど焼きをやる場所がない! なんて事はなかったように記憶しています。でも、今ではそんな場所すらありません。7MHzの逆Vですら苦労するご時世ですからhi
もし、近くで行われているようであれば、今年はもう遅いですが、来年参加してみてはいかがでしょうか? 余談ですが、日本以外にも、どんど焼きに似た行事が、世界各地にも存在しているそうです。調べて見るのも楽しそうですね。

どんど焼き
恵方巻きの由来
今年の恵方巻き、そしてその始まりについて気になりますよね! ちなみに2025年の恵方は「西南西」です。
恵方巻きの由来と方角について
恵方巻きを食べる習慣は、近年広まったもので、その起源は諸説あります。
陰陽道との関連: 陰陽道では、その年の福徳を司る年神様がいる方向(恵方)に向かって事を行なえば、「何ごとも吉」とされました。この考えが、恵方巻きを食べる習慣に繋がったという説があります。
商売の発展: 関西地方の寿司屋が、節分の時期に巻き寿司の販売促進のために始めたという説も有力です。
恵方の方角は、毎年変わります。これは、年神様がいる方向が毎年変わるためです。恵方は、主に東北東、西南西、南南東、北北西の4つの方向のいずれかになります。
恵方巻きの始まり
恵方巻きの起源は諸説あり、はっきりとしたことはわかっていませんが、大阪が発祥という説が有力です。江戸時代に、節分の日に太巻き寿司を丸かぶりして無病息災を願う風習があったという説。戦後に、大阪の海苔問屋が考案し、販促活動の一環として広まったという説などがあります。
恵方巻きの特徴と意味
恵方を向く: その年の恵方に向かって、願い事を心の中で唱えながら食べます。
丸かぶり: 巻き寿司を切らずに丸かぶりすることで、「縁を切らない」「福を巻き込む」などの意味があります。
具材: 一般的に、七福神にちなんで7種類の具材が入っていることが多いです。具材にはそれぞれ意味があり、「長寿」「健康」「富」など、良いことがたくさん詰まっています。
恵方巻きが人気になった理由
手軽に楽しめる: 家族や友人と一緒にお祝いできる手軽さ
縁起が良い: 願い事を叶えてくれるという縁起担ぎ
バリエーション豊富: さまざまな具材や味の恵方巻きが楽しめる
など、さまざまな理由が考えられます。
まとめ
恵方巻きは、日本ならではの風習として、多くの人々に親しまれています。今年の恵方巻きを食べる際には、ぜひその年の恵方(2025年は西南西)の方角を確認して、願いを込めて食べてみてはいかがでしょうか。

恵方巻き
QSOパーティはいかがでしたか?
今年のQSOパーティへ参加さたれ皆さんはいかがでしたでしょうか? 最低ノルマの20局はできましたか? 私は年始に発熱してしまい、残念ながら20局できませんでした。まあ、今年を逃したことで、12年後頑張ればいいや、と思ってきていますhi それより12年後にムセンを楽しめるだけの健康状態が保たれているかが心配ですが。
目標が出来たことで(とはいえかなり苦しい目標ですがhi)しばらくはアクティビティが保てると思っています。最近のアクティビティの低下は、常設の無線設備がないこと、出先で手軽にオンエア出来る設備が整っていないこと、この2点ではないかと思います。ローカルさんにはずっと言われ続けていますが、まずは設備を整え、新たなことに挑戦をしていきたいと考えています。

早く復活させないと・・・
春先に向けて
この原稿が皆さんの目に触れるのが2月3日。2月は日付が他の月よりも少ないので、あっという間に3月になってしまいます。1年の中で一番寒いと言われている時期ではありますが、春になってからの準備をしておきましょう。(自分に一番言い聞かせてますhi)
さて、2月が他の月よりも日数が少ないのは、歴史的な経緯が大きく関わっています。
2月が他の月よりも短い理由
古代ローマの暦: 現在の暦の基礎となった古代ローマの暦では、1年の始まりは3月でした。そのため、2月は1年の最後の月にあたっていたのです。
閏年の調整: 地球の公転周期は正確に365日ではないため、暦と実際の季節がずれてしまうのを防ぐために閏年が設けられました。この閏日を調整するために、1年の最後の月であった2月の日数が調整されることになったのです。
偶数と奇数: 古代ローマでは、偶数は不吉な数と考えられていました。そのため、多くの月は奇数の日数で構成され、2月だけが偶数の28日とされていたのです。
2月が短いことになった歴史的な流れ
ローマ暦: 初期のローマ暦は、1年が304日と非常に短く、季節と暦が大きくずれていました。
ヌマ暦: ローマ王ヌマ・ポンピリウスによって、1年を355日に修正された暦が作られました。この暦では、2月が1年の最後の月で、偶数の28日とされていました。
ユリウス暦: ユリウス・カエサルによって、1年を365日(閏年を4年に1回)とするユリウス暦が導入されました。この暦でも、2月は1年の最後の月としての位置づけが残り、閏年の調整に使われる月となりました。
まとめ
2月が短いのは、古代ローマの暦の仕組みや、閏年の調整、そして偶数と奇数に対する考え方が複雑に絡み合った結果です。歴史的な経緯を辿ると、2月がなぜ他の月よりも短いのか、その理由が見えてきます。

2月は他の月よりも短いのには理由があります
節分について
節分とは、立春の前日のことで、季節の変わり目に邪気を払い、新しい季節を清々しく迎えるための行事です。古くから日本で行われてきた伝統的なもので、「節分」という言葉には「季節を分ける」という意味があります。
節分の由来と歴史
季節の変わり目: 昔の人々は、季節の変わり目は邪気が入りやすいと考え、その邪気を払うために節分を行うようになりました。
鬼を追い出す: 節分には、豆をまいて「鬼は外、福は内」と唱える風習があります。これは、年の悪いものを鬼に見立てて追い出し、福を呼び込むという意味が込められています。
中国とのつながり: 節分の起源は中国にあるという説もあります。中国の陰陽五行説に基づき、季節の変わり目に邪気を払う行事が日本に伝わり、独自の風習として発展したと考えられています。
節分の行事
豆まき: 炒った大豆をまいて「鬼は外、福は内」と唱えながら、家の中の鬼を追い出すのが一般的です。
恵方巻き: 恵方と呼ばれる吉の方角に向かって、太巻きを無言で食べながら願い事をすると、その年の願いが叶うと言われています。(恵方巻きについては本稿の最初をご覧ください)
節分そば: 一年の締めくくりとして、そばを食べる地域もあります。
節分の意味
一年の無病息災: 家族の健康を願い、邪気を払うことで一年を無事に過ごせるようにと願います。
福を招く: 福を呼び込み、新しい一年を良いスタートで迎えられるようにと願います。
邪気を払う: 年の悪いものを追い出し、心身を清めることで、新たな気持ちで一年を始められます。
現代の節分
現代では、節分は家族で一緒に過ごすイベントとして定着しています。豆まきや恵方巻きだけでなく、節分をテーマにしたイベントや商品なども多く見られます。
まとめ
節分は、古くから続く日本の伝統的な行事です。季節の変わり目に邪気を払い、新しい年を良いスタートで迎えられるようにと願う、大切な行事と言えるでしょう。

年の数だけ豆を食べる風習もありますね
なおご意見、ご感想、ご質問等については、筆者である私宛(jf1kktアットマークgmail.com)へご連絡頂けますと幸いです。
アマチュア無線の今と昔 バックナンバー
- 第39回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ
- 第38回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ
- 第37回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ
- 第36回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ
- 第35回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ
- 第34回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ
- 第33回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ
- 第32回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ
- 第31回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ
- 第30回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ
- 第29回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ
- 第28回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ
- 第27回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ
- 第26回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ
- 第25回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ
- 第24回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ
- 第23回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ
- 第22回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ
- 第21回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ
- 第20回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ
- 第19回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ
- 第18回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ
- 第17回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ
- 第16回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ
- 第15回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ
- 第14回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ
- 第13回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ
- 第12回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ
- 第11回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ
- 第10回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ
- 第9回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ
- 第8回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ
- 第7回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ
- 第6回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ
- 第5回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ
- 第4回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ
- 第3回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ
- 第2回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ
- 第1回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ
外部リンク
アマチュア無線関連機関/団体
各総合通信局/総合通信事務所
アマチュア無線機器メーカー(JAIA会員)