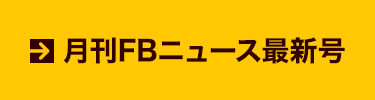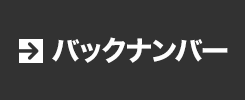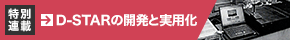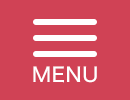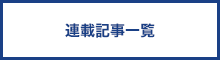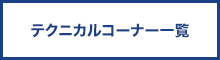おきらくゴク楽自己くんれん
その46 QSOパーティを前に100W太陽光パネル搭載
2025年2月3日掲載

皆さんこんにちは。年が明けQSOパーティを迎えました。「今年もよろしくお願いします。」と新年のあいさつができるQSOパーティは大変アマチュア無線家向きのいい行事だと思っています。最近は新しいモードが増えていますが、このパーティ期間くらいは電話モードを使って自分の声であいさつを交わすようにしたいと思っています。
毎年初日の1/2は奈良県山辺郡山添村から移動運用で参加しており、今年で連続33回を数えることとなりました。33年の間には積雪や吹雪の中での運用や強風でアンテナがあげられなかった日があったかと思えば、春みたいに暖かい穏やかな日などいろいろなことがありましたが今年は気温は低いものの日差しもあり風も弱くてまずまずの良い天気となりました。
今回は4WD軽トラとモバイルシャック暖房(セラミックファンヒーター)設備などが整った状態で移動運用に挑めます。QSOパーティ期間中全ての日で移動運用をして、期間後半に相手探しに苦労している局の助けになればと思います。その前に昨年末、ついついネット通販のセールに購入してしまった物でやり残してしまったことを、家族サービスそっちのけで元旦からごそごそ作業に励んでしまいました(笑)。
1. モバイルシャックの電源事情
このモバイルシャックを作った時、無線機用も含め電源は室内に当時持っていた容量50Ahや30Ahの12.8Vリン酸鉄リチウムイオン電池と理想ダイオードで逆流を防止したDC分電盤で軽トラックの鉛バッテリーから供給する2系統を用意していました。使っているうちに100Ahの電池に容量アップ、ついには230Ahの電池まで購入して無線機電源以外にシャック内冷暖房まで賄うようになってきました。
230Ahとなるとコンテスト移動運用でマルチバンド部門に50W出力で24時間使用したとして余るくらいの容量がありますが、旅行がてらのキャンピングカー的使用では冷暖房の電源として使用すると一夜を越すと不足してしまいます。何日も移動が続くような時は途中のどこかでAC電源を使い充電する必要がでてきます。しかしそれらのサービスを外出先で得ようとすると結構大変です。
例えばキャンプ場や車中泊施設など何かの施設を利用することによる付帯する電源サービスしかないのが現状です。しかしこれでは単独で寝泊まりすることができるモバイルシャックでは不整合で不経済です。どこかのテレビ番組のように見ず知らずの人に「充電させてください」と頼む訳にもいかないですね。
ということで旅中にいくら電源があっても困ることはない、というかできる限りの方法で電源が確保することは必要だと常々と感じておりました。
2. 太陽光ですか?
これまでローカル局からやアマチュア無線イベントなどで見学していただいた方々からよく、「やっぱり電源は太陽光ですか?」と聞かれます。「リチウムイオン電池に貯めています」と説明しましたがちょっとしたSDGs圧力を感じておりました(笑)。
モバイルシャックを作るもっと前から太陽光だけで無線運用のエネルギーを賄ってみたいとは思っていましたし、モバイルシャックという都合のいいアイテムがあるのですから太陽光パネルを採用しない話はないように思えます。しかし簡単にはできない理由があります。
モバイルシャック設計時に本体高さをどれくらいにするかは室内での快適性を重視してできるだけ高くしたかったのですが、家で保管する場所の屋根の高さの制限がありました。そこでシャックをギリギリ高くしたので必然的にシャック屋根と保管場所屋根との間隔が少なくなりました。
はじめは問題なかったのですが載せ降ろしの度に作業が段々おろそかになり、時々勢い余ってシャック屋根のガルバリウム鋼板が保管場所の屋根を支えるパイプ継ぎ手に屋根が当たって数ヵ所凹ましておりました。もしここに太陽光パネルつけていたら? シャックの屋根一面にパネルを敷けば300W~400Wの発電が見込めたと思いますが、こういった理由で屋根に太陽光パネルを載せることは無理と判断しておりました。

シャック保管場所上部のクリアランス
それに電源を扱うデバイスを使うと出てくるノイズが気になります。できる限りネガティブなものは避けたいという気持ちも大きかったことも太陽光導入を考えていなかった理由の一つでした。
3. 諦めていたものの
ところが昨年末、某ネット通販のセールで100Wパネルとコントローラーが安くなって売られているのが目にとまりました(後で知ったのですが、これはその時だけでなく年が明けてからも同じ値段で売られていました)。以前にも同価格になっていたのを何度か見かけましたが購入はしませんでした。仕様では期待できる一日の発電量は0.4kWhということです。どう取り付けるのか? 付けてどう活用するのか?
あとで考えましょうのやってみよう精神で、その時の私の心の中は大きく揺れました(汗)

100W太陽光パネルセットを開封
届いた商品は100Wパネル、30A充電コントローラー(PWM)、コネクター付きケーブル、パネル取り付け金具と説明書などです。パネルの大きさは1010mm×480mm×35mmです。
どう取り付けるか? モバイルシャックは都度載せ降ろしするので作業に干渉しない場所にしなければならず「シャック側面に常設」とか考えましたが、縦置きでは発電効率が悪そうですし答えが出ませんでした。結局課題は先送りにして年内の忙しい予定をこなしながら購入したままの形で放置が続き、新年を迎えてしましました。
そして新しい年を迎え「ええい、悩んでも仕方ない!」と昨年までの気持ちの揺らぎは何のその、正反対の切り替わった気持ちが生まれ、元旦から運転席上部に取り付ける作業をしました。もしも都合が悪いようであれば外せばいいだけだ、と思い切り。それにこの位置ならモバイルシャック高速走行時の空気抵抗を減らす(フラッシュサーフェイス化)ことも期待したりします。

この位置に決定
元旦は午後からお天気にも恵まれ、程なくパネルの取り付け作業はできました。搭載後テスト走行で問題なく走ることを確認。この日、高速道路は走らなかったのですが法定速度が70㎞/hの道路ではこれまでより風切り音が減り抵抗が少なくなった感じがしました。高速走行時、運転席上の天板とモバイルシャックとの間で渦巻いていたであろう空気を整流する効果がそれなりに出たのでないか? と考えています。
しかしその根拠となるデーターは一切ありませんので気分だけの改善、いわゆる「プラシーボ効果」なのかもしれません(笑)。気分よく高速道を走ることができれば一番です。今後の走りや燃費などで違いが出てくれることを期待します。
セットに付属していたケーブルは本来パネルを家屋の屋根につけて引き込むことを考えているものですから、軽トラックに載せるには十分な長さがあります。しかしこのケーブル長は、家につけて引き込むのに十分な長さかというとちょっと足りないように思います。しかし価格が価格だけに仕方のないことなのでしょう。

20Aソーラーチャージャー(PWM方式)
付属のソーラーチャージャーはシャック内前方壁に取り付け、230Ahのリン酸鉄リチウムイオン電池に接続しました。正面の液晶表示により電池電圧、充電電流、12V負荷への出力電流、コントローラー温度などの情報を得ることができます。DC12V負荷(実際には電池電圧?)は、製品説明では30Aまでの電流を取り出せるとありましたが端子の大きさからそこまで流せるとは思えません。それでもテストで19Aを出力させることができました。とりあえず隣のDC分電盤に接続して無線機電源を供給します。おまけにUSB-Aポートが2つあり、室内でのスマートフォンやIC-705の充電などに重宝しそうです。またこの機種の充電方式は格安ソーラーチャージャーの主流であるPWM充電方式のようです。
取り付け配線が完了すると早速パネルからの電気で充電が始まります。しかしシャック保管場所の日当たりはあまり良くありません。この季節の太陽の高さでは自宅前の林の向こう側を太陽が移動するため、時々しか日が当たりません。ここではせいぜい5~20W程度の発電しか見込めないので少し移動させます。
しかし我が家では15時にもなると日が山の向こうに落ちてしまい、たちまち発電量が減少します。この日は電池にエネルギーを補充できた実感(電池電圧の変化等)は得られませんでした。
4. 2025年QSOパーティ全日移動運用
翌日の1/2となりました。100Wソーラーパネルを載せた状態で初の移動運用に参ります。昨日テスト走行はしましたがパネルを付けて目的のある走行は初めてとなるので慎重に運転しました。
1月2日 奈良県山辺郡山添村移動

1/2の移動運用風景
50MHzデルタループと430MHzは1.5m長のモービルホイップアンテナを使用し37局と新年のあいさつができました。午後の日差しがちょうど停車位置の正面となり約60Wのソーラー発電を確認することができました。といっても雲が少しでもかかると充電量が下がっていくのでよほど条件が整ってないと出ない数値です。
1月3日 奈良県吉野郡東吉野村移動
870mくらいの高さの山の上です。38局と交信することができました。昼間は家族との時間がありましたので、夕方からの出発で430MHzのみで簡単移動運用でした。「クマ出没注意」の看板があったのですが、出没したのは離れた場所でしたし夜なのでそれ程怖くはありませんでした。真っ暗な場所だった為運用写真は撮れませんでした。
1月4日 奈良県奈良市移動
高台からの運用で50MHzと430MHzで26局と交信することができました。この日はパネルと太陽を理想的な角度で向けることができたので75W程度の充電を確認できました。100Wパネルとは言っても実際に100Wが出力される訳ではありません。日射角やパネルの温度など様々な条件で変化してしまいます。

1/4の移動運用風景
1月5日 奈良県宇陀市移動
宇陀市の標高700mくらいのところから50MHzで運用しました。22局と交信することができました。写真では天気がいいように見えるのですが、この場所に日が当たるのは午前中だけなので十分な日光を浴びることはありませんでした。

1/5の移動運用風景
1月6日 奈良県奈良市移動
この日は夜間に高台のサービスエリアで移動運用しました。430MHzと144MHzで8局と交信することができました。
1月7日 奈良県山辺郡山添村移動
最終日です。平日でしたが午後遅く山添村内のダム湖のほとりで、7MHzの7mh逆Vダイポールを使い6局と交信することができました。これで全日移動運用することはできました。日が傾いてからの運用で十分な日光を浴びることはできませんでした。全体的に気候に恵まれたQSOパーティ期間でしたが太陽光的には今一つでありました。期間中交信していただいた皆さんありがとうございました。
5. 100W太陽光パネル容量について
今回のQSOパーティは平日が多かったので、夜間運用が増えて太陽光パネルの実力テストには今一つでした。運用風景写真ではお天気に恵まれたくさん日光を浴びたように感じますが冬なのですぐ雲が多く隠れてしまいますし、日没時刻も早くなかなか恩恵を実感することはありませんでした。雲が被るとすぐに10W以下まで充電が減ってしまいます。おかげでどの程度の日射でどの程度発電量があるか想像できるようにはなりました。
そもそも1日に0.4kWhの発電量しか見込めないセットです。これは230Ahのリチウムイン電池2.9kWhの容量の13%にしか過ぎません。もともと太陽光パネルは天候に大きく左右される不確実なエネルギー源ですし、普段の使用では電池容量を継ぎ足すものとして程度の期待をしておくべきでしょう。何日かにわたる長距離移動で一日無線をした翌日に天気が良ければ0.4kWhの容量が継ぎ足されるという考えです。そんなことは起こらないと思いますが、災害でインフラが破壊され、あらゆる電源が失われた時に太陽さえ出れば通信に使用する電源は確保できるとものと考えましょうか。無いよりあった方がいい設備です。
気になるノイズ問題ですが、充電コントローラーは電源が入った時点で弱いノイズが広い帯域で出ていることが確認できました。シビアな通信状況ではコントローラーの動作そのものを止めるスイッチが必要かもしれません。おまけ? のUSB端子ですがこれは使用すると強力なノイズが発生する曲者機能でした。無線運用と同時にUSB端子を利用することはできないような状況です。
またこのPWM方式のコントローラーは十分な光量が得られないときの充電効率があまり良くないという情報も聞きましたのでコントローラーの入れ替え等、充電効率の改善方法を費用等も含め検討したいと思っています。
おきらくゴク楽自己くんれん バックナンバー
- その56 ポータブルインバーター発電機の導入
- その55 アイコムフェアin東京両国訪問と無線用電源考察
- その54 悩み多きモバイルシャックの空調と電源
- その53 ハムフェア行脚で太陽光パネル風防効果を実感
- その52 モバイルシャックの太陽光パネルをパワーアップ
- その51 6m AND DOWN コンテストと記念局公開運用参加
- その50 軽トラモバイルシャック用HFアンテナを考える
- その49 移動運用で確かめるモバイルシャック装備とルームツアー
- その48 最大落差!? 全国ランキング1位と日本一ダメな道の駅で移動運用
- その47 話題のミニPCはモバイルシャックに最適でした
- その46 QSOパーティを前に100W太陽光パネル搭載
- その45 暖房設備充実で雪中移動運用を満喫
- その44 軽トラモバイルシャックのユーティリティーについて
- その43 IC-705とAH-730で快適QRP運用
- その42 暑さ対策万全の軽トラモバイルシャックでハムフェア
- その41 軽トラモバイルシャック夏対策2
- その40 6m AND DOWNコンテスト移動運用で軽トラモバイルシャック夏対策
- その39 ALL JAコンテストに50MHzポケットダイポールVer.2で参戦
- その38 三重県移動運用とバーチカルアンテナの改良
- その37 モバイルシャックと軽トラのハイブリッド移動で春の移動運用三昧
- その36 軽トラモバイルシャック九州ツアーで全都道府県移動を達成
- その35 軽トラモバイルシャック九州ツアーで全都道府県移動を達成目前
- その34 全都道府県移動運用完成を目指す九州ツアーを敢行
- その33 秋のJARL地方支部大会行脚でトラブル発生
- その32 軽トラモバイルシャックの改良
- その31 144MHz帯ツインループアンテナで全市全郡コンテストに参戦
- その30 2023年 モバイルシャックで初めての夏
- その29 2023年 フィールドデーコンテスト遠征参戦
- その28 2023年 6m AND DOWNコンテスト参戦記
- その27 軽トラモバイルシャックの快適化
- その26 材料費高騰に対応! 移動専用144MHz帯ツインデルタループアンテナの製作
- その25 軽トラモバイルシャックのご質問にお答えします
- その24 軽トラモバイルシャックで行く西日本ハムフェア
- その23 軽トラック荷台移動運用シャックにAH-730を搭載!
- その22 軽トラック荷台移動運用シャックでQSOパーティ
- その21 軽トラック荷台に載せる移動運用シャックを作る-7
- その20 軽トラック荷台に載せる移動運用シャックを作る-6
- その19 軽トラック荷台に載せる移動運用シャックを作る-5
- その18 製作途中の移動運用シャックを積んでハムフェアに
- その17 軽トラック荷台に載せる移動運用シャックを作る-4
- その16 軽トラック荷台に載せる移動運用シャックを作る-3
- その15 軽トラック荷台に載せる移動運用シャックを作る-2
- その14 軽トラック荷台に載せる移動運用シャックを作る-1
- その13 格安飛行機(LCC)を利用しての九州南部で移動運用
- その12 50MHz片側電圧給電(ツェップライク)アンテナの製作
- その11 ローコスト7MHz逆V型ダイポールアンテナの製作
- その10 リチウムイオンサブバッテリー使用リポート
- その9 サブバッテリーをリン酸鉄リチウムイオン電池にしてみる
- その8 今どきの軽自動車へのモービル機取付け
- その7 本記事での製作品を活用して挑む 全市全郡コンテストQRP参戦記
- その6 変角ロッドアンテナを使って省スペースな50MHz折り曲げ式ダブルバズーカアンテナの製作
- その5 【格安溶接機で作る移動用タイヤ踏みベース】
- その4 【格安の直流インバーター溶接機で】 お手軽移動用タイヤ踏みベースを作る
- その3 HFJ-350M二刀流!? マルチバンドホイップのVダイポール化
- その2 50MHzポケットダイポールアンテナで入賞を目指す!? ~ALL JAコンテスト参戦記~
- その1 携帯性抜群!50MHzポケットダイポールアンテナ
外部リンク
アマチュア無線関連機関/団体
各総合通信局/総合通信事務所
アマチュア無線機器メーカー(JAIA会員)